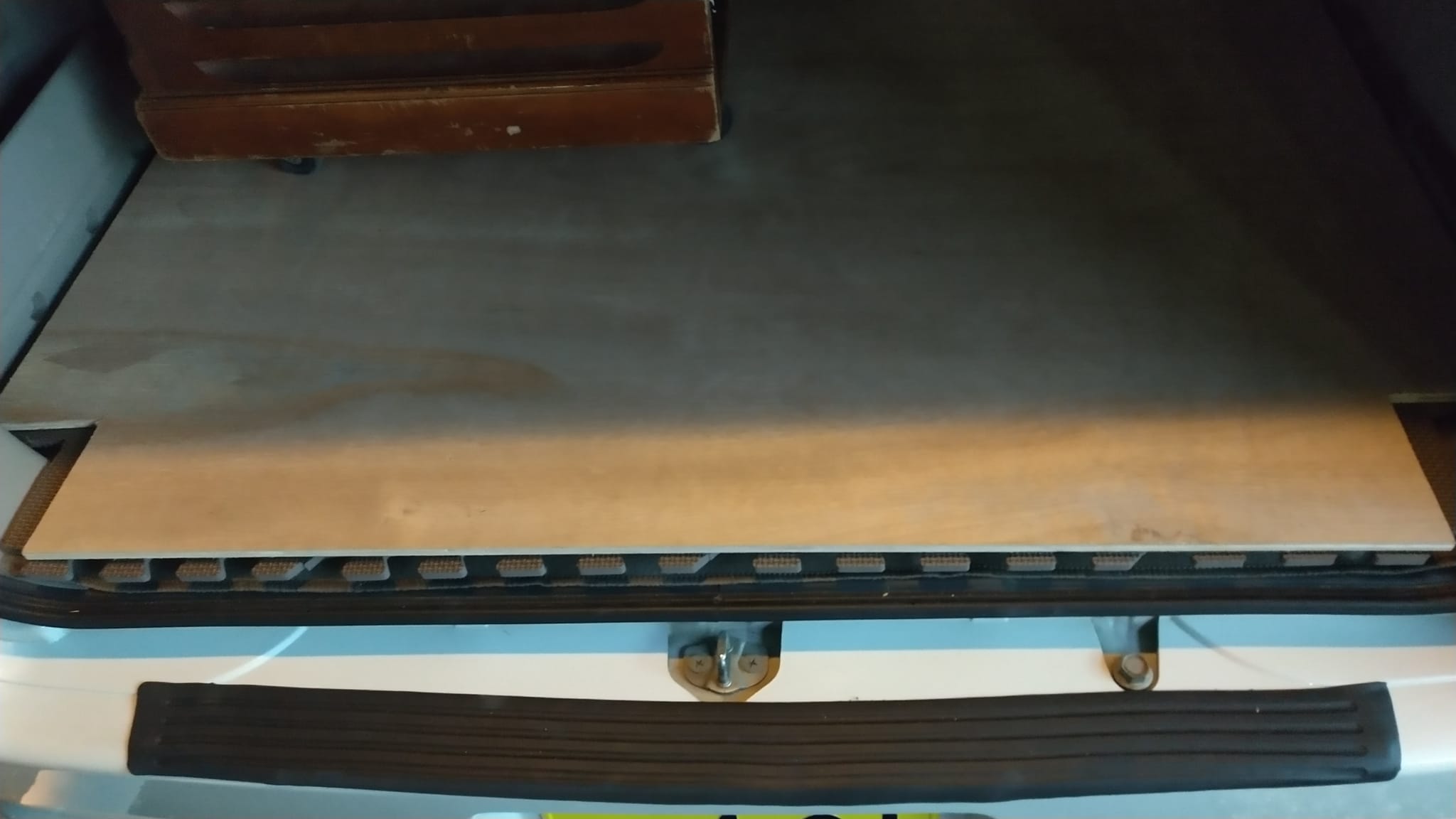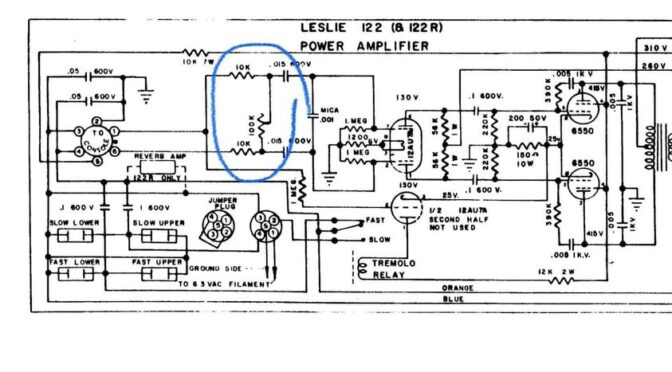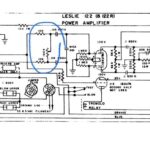自作Fender Champの高域がぜんぜんでなくて悲しかった問題ですが、RC Boosterのコピー品?ぽいクリーンブースターを使うことにしました。
これだけでも高域と低域をかなりいい感じにいじれます。
日によってとか時間経過とかですこしEQいじりたくなる気持ちになるときに簡単に変えられるのが本当に便利です。
足りなかった高域がでます!
チャーリークリスチャンピックアップの音がしてくれる!
ついでにエフェクターのゲインを上げればだいぶ余裕の音量感でアンプからの音も強くできる(ちょっと張りがありすぎてなんかゲイン上げたなあという音なので音圧が足りない時にですね)
それに伴いエフェクター使う前提になったので、アンプのつまみを減らしてエフェクター用電源をパネル部分からとれるようにしたすっきりデザインにしてみました。
無駄な配線がない感じです。
というわけで以下そのショート動画と説明文です。
アンプ微修正。
つまみをいろいろつけてたけど、クリーンブースターをつけることでとりあえずVolumeと簡易的なMIdとデジタルリバーブの3つでよいかなと。
2つ穴があまったので一つはエフェクター使うし一応ジャックの入力抵抗を可変にしておきました。
まあ正直なくてもよいけど。
もう一つは9Vの直流電源を取り付けて動画のように簡単にエフェクターをつなげられるようにしてみました。
アンプの電源とも連動するので便利です。
これは個人的に大成功。
すっきりです。
EQとかの音づくりはクリーンブースターでいろいろできるのでようやくこのアンプである程度よいかなあという音が出来上がりました。 プリプリしたシングルトーンが出てくれるのはしあわせですな。 ほんとは中に回路仕込みたかったけど、また発振?してもなあというところだったのでやめときました。