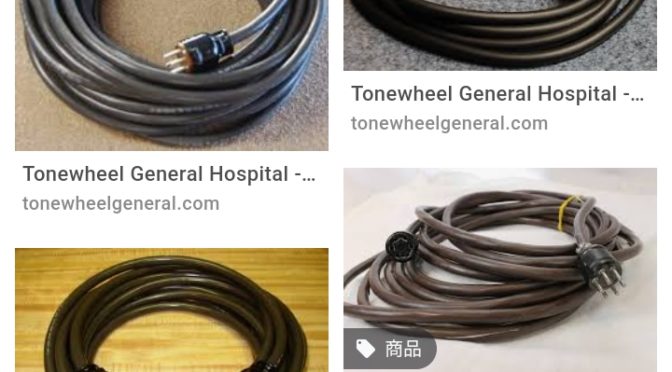「2103mk2」タグアーカイブ
レスリー2103mk2スピーカー交換142との比較レビュー的な

レスリー2103mk2と142のスピーカー配線材かえたけど
レスリー2103mk2ビビり解消
レスリー2103mk2内部配線つづき
レスリー2103mk2メンテナンスなど
ライブ用のレスリー142音が出なくなる
現在の電源ケーブルのつなぎ方
まあ日々予算の範囲内でいろいろ実験しているわけですが、
最近手に入れたナノテック308という割とお高いケーブルを使いすぎると低音の重心がEQのBassより低い位置にいってくれるかわりに、現行モデルのオルガンとレスリースピーカーだと音の真ん中が弱くなってしまうという問題も発見されました。
メロディ弾いたり、コード弾いたときにちょっと弱いみたいな。
かといってここ数年メインのオヤイデのLi/50OFCというケーブル
(これはこれでよいのですけど、2スケア×2だとどうやら重心は重心はちょっと低くなってくれない、だが真ん中はいい感じ)
だけだとちょっとローミッドの癖が気になるというわけで、
ここで癖のないと思われるCANARE LP-3V35ACを投入してみようというわけです。
というわけでちょっと試したところのセッティングは以下の通りです。
・ライブ用NordC2DとLeslie2103mk2の組み合わせの場合
壁→カナレ→電源タップ→Li/50→NordC2D
→ナノテック308→Leslie2103
・自宅Hammond B3の場合
壁→Li/50→UPS(トランス的に使ってます)→ナノテック308→B3
自宅用のB3にはもともと電源タップも通したりしておりましたが、家庭用だと低音も強すぎるので、このくらいでも十分です。
ビンテージのオルガンだと中域の物足りなさは感じないからこれでよいくらいです。
しいて言うなら音の立ち上がりが若干速くなるとより好ましいくらいですかね。
ライブ用の機材は壁から電源タップまでを無味で音やせしなさそうなカナレにしてみたのですが、これでもまだ中域もう少し欲しいのでここもやっぱりLi/50にしてもよいかなあとも悩みどころです。
いま梅雨で湿度高いから音がちょっと判断しづらいということも悩みの一つです。
基本的には一本はナノテック308をどこかしらに入れないと、
低域の重心が下がってくれないから必ず必要です。
ただこれも壁からタップまでなのか、オルガンにつなぐべきなのか、これまで通りレスリーにつなぐのかまだ結論ははっきり出ておりません。
部屋のなり方にもよりますし。
とりあえずこの組み合わせでも割といい音にはなるよとだけしか言えませんね。
タップのコンセント部分の種類の組み合わせやケーブルの組み合わせでもう一息よい音色にまでもっていくべく研究してみます。
結構いい線まできてるはずです。
最近の改造、レスリー2103
前回どこまで行ったか忘れましたが、とりあえずレスリー2103の下に取り付けているハコを主に修正しました。ほかにもちょこちょこ。
・ハコの高さ
20センチほど切ってみました。
2103の高さとあわせて100センチちょうどくらい。
ビンテージレスリーとだいたい同じくらいの高さですかね。
ドラマーがスピーカーに隠れて見えなくなることはなくなったし、座ると耳の高さにあったホーンの位置が下がって耳元でうるさいということはなくなったかも。
・2103内部の吸音
どうしても低音に強くなりすぎるキーがあるので、とりあえず吸音材多めにつめてます。スピーカーの特性がそのままでてくれればよいのだけど、なかなかそうもいかない。
ちょっとはなだらかになったかもです。
吸音材つめると響きが減るのがなやみどころ。
・内部配線
ビンテージスピーカーでいろいろ試した結果、現行の線で一番良さそうなのがベルデン8460ぽかったので、それを2103に使ってみました。とりあえずホーンドライバのとこだけ。
基板への取り付けがちょっと手間でしたが、端子に無理やりはんだで留めて無駄無い情報の伝達を期待してみました。
音がどう変わったか憶えてないけど、現状結構いい音してると思います。
・11ピンケーブル
11ピンのうち、自分の使い方だと6ピン分しか使ってなかったぽいので、ビンテージ6ピンケーブルで11ピンケーブルを作りました。むりやり。
ここの線はほんといろいろ試したけど、これが一番あうかも。現行の高級でレンジが広い線とか聴き疲れするし。
意外にハモンドオルガンの音はもともとレンジ狭めのケーブルの音だから聴き疲れしないのかも。
このケーブルの欠点は固すぎて取り回ししにくいというところです。
改良方法を模索中。
・低音のスピーカー交換
もともとのがだいぶへたって目一杯出すとスピーカーのエッジがぶるぶるなるので交換してみました。
せっかくなので少ない選択肢ながらAmazonで探してDayton Audioというメーカーのものにしてみました。
今のところ特別不具合もないので、リプレースの選択肢としてはありかも。
他の安いやつとかも試してみたいけど、、、。
とまあいろいろやってます。
おかげでかなりよい音なのでいつも使ってるNord C2DとこのLeslie2103の組み合わせでの音も聴いてほしいです。
よろしくお願いいたします。
6ピンケーブルで11ピンケーブル作った
何を言ってるかよくわからないかもしれませんので、説明しましょう。
音をよくするための苦労です。
現行のオルガンとレスリースピーカーをつなぐケーブルは特殊な仕様の11ピンのケーブルを使うのですが、そのケーブル部分のみ、ビンテージハモンドオルガンとレスリースピーカーをつなぐ6ピンケーブルで作ってしまおうという実験です。
端子の数に対してケーブルの数が少ないとか、そもそも意味あるのかとか疑問を抱かれるかもしれませんが、これまでの実験から既に、少なくともオルガンの音だけ使うためには、6芯のケーブルで十分なのです。
さらに言ってしまえば、音声信号の線は1つなので、それだけ別に這わせればその音になります。他はレスリーのslow fastとかなのでケーブルが特別よい必要はないです。
まあ今回は6芯ケーブルを破壊したくなかったし、これでなんとか収まったから良かったです。
あと6ピンケーブルは11ピンケーブルよりもはるかに太いというのも大きな違いです。というかそれだけが目当て。
これまでは細い適当な多芯ケーブルの横に一本だけいろいろな線を這わせて、それぞれの音を確かめたりしてみました。
その結果わかったことは、レンジが広いケーブルはオルガンだと聴き疲れする。真ん中あたりが細くなる。そもそもビンテージハモンドオルガンの音は実はそれ程レンジが広い音ではない。
そういうよさげなケーブルやギターケーブルよりも、11ピンケーブルのかなり細いケーブルの方がオルガンの音としてはよさげ。
しかも11ピンケーブルも日本の本家のメーカーのものより、海外のパーツサイトの方が音は好み(見た目も固さも全然ちがう)。
しばらくは海外から取り寄せた11ピンケーブルを使っておりましたが、好奇心には勝てず、6ピンケーブルだとどうなんだろうという流れです。
結果、さらに音がよくなりました。
ケーブル同様太みがありますな、太みが。
問題はケーブル自体がものすごい固くて曲がりにくく、太さと重さもあって取り回しも大変ですが、端子痛めないか心配になるくらいです。
これに関しては今また別の方法を考え中。
そして同時に、レスリー122への変換器のケーブルもこの仕様にしてみたり。これは内部は苦労したけど、できたぽい。
レスリー147への変換器はただいま取り組み中。こちらは数年前に試しに国内の業者(メーカーでないとこ)に頼んで作ってもらったけど、正直ケーブルの長さが注文した仕様とも違ったし(使いにくい)、ケーブル自体もオルガン用のものでもなく、音が悪いものなのでこちらこそやらねば。
一応オルガン専門にやってるとこなら仕様のミスもだけど、ケーブルの値段けちらないでちゃんと音質まで考えて欲しいですなあ。
というわけでやることいっぱい。
Leslie2103改造、バスレフ対策
下に大きなハコは相変わらずしいております。
まあとにかくLeslie2103の低音が音によってばらつきが大きいのでなんとかしようという企画のつづきの実験です。
今回もいろいろやってしまいました。
まずはまた大きな穴を空けました。
前に下向きに四角く切ったのは真ん中でその横に大きな丸い穴を2つ。
試しに前向きについている13センチウーハー×2を下向きにつけたらどうなるかという実験です。
音は悪くなかったけど、ゴム足の部分があるので、カバーをつけないとさすがに運搬時に危険なので元に戻しました。
穴を空けたのはスピーカーを取り付けてみるというのもあったのですが、とにかくバスレフ音がいやだったということで穴あけたら解決するかなという発想です。
実際の効果の程はどれくらいかはいまいちわかりません。というのも同時に吸音材をさらに詰めまくったからです。
その結果締まりのあるよい低音にになりました。低音も十分でてます。これまでが出すぎみたいな。
ベース音のてこぼこもほぼなくなりました。Eの音だけほんの少し持ち上がるので、定在波なのか、何かの固有振動数なのかもなあというくらいです。
効果てきめん。
もう少しつめこんでもよいかも。
しばらくこれでいってまた様子を見ますが、今回の変化はかなりいいと思います。
レスリー2103の下のハコ作りました。もっと大きいの。
以前作ったレスリー2103用の下のハコ(高さ45センチ)もよかったのですが、もっとハコの容積を大きくしたらより豊かな低音になると期待しておりました。
が、あまり大きくすると携帯性も低くなるしという悩みもあります。
というわけでとりあえず作ってみました(笑)。
板の歩留まりが悪すぎて材料に結果二枚の板を使いハコだけで高さ90センチになりました。
全部で120センチくらいでしょうか。
一般的な大きなレスリーが102センチとかなので、かなりでかいです。
下は純粋に空洞なので、ハコなりスペースは122よりもかなりおおきくなっております。
工作もここまで大きいと板の曲がりも大変で、建て付けの悪さもあり、びびりもありますが、そこらへんは調整してみました。
音はやはりよいですね。うるさくなく大きく出せるし、高音部との分離がよくていいかんじです。
もちろん今回も折りたためるので、いまだに台車一回で移動可能。
車をツアーの3人乗り仕様にしても載せられるのは大きな進歩ですね。
スピーカー本来の定在波もいろいろ減らす工夫ももっとしないと。
みんなにきいてもらえるのがたのしみです。
11ピンケーブル作りました
現行モデルのオルガンとレスリースピーカーにつなぐ専用の11ピンケーブルがあります。
特殊な形状なので作るのも大変。よい線材を使うにしても、多芯ケーブルには材料も限られるわけで、なかなか手を出せませんでした。
市販のものは長さが7メートルとかなり長く、音質の劣化もありそう。
ということで今回は5メートルでつくります。
こういうことができるようになったのも、いろいろな実験で経験がついたからですなあ。
というわけで完成しました。
普通の多芯ケーブルと音声信号のみよさげなケーブルを使ってそれらをメッシュで覆って完成。
さて、肝心の音ですが、音色的には全体的にレンジが広がって高級感が出ました。
低音も当初の目的通り芯のある感じになりました。
音圧、音量は下がりましたが当初は低音が強すぎたりしたし、出力的にもかなりまだ余裕があるので、問題ありません。むしろ強すぎたくらいなので。
一番予想外の違いが、発音の速さが全然違ってきこえるというところです。なんだこれ。
今までに比べてスピードは落ちたと思います。
これが果たしてよいのか悪いのかわかりませんが、自分的にはタイミングはとりやすいかもです。不思議です。
楽器の発音のタイミングが望み通りにでるかって音楽人生がかわるんじゃないかってくらい大事なことと思うのですが、それが線で変わってしまうなんて、、、。
というわけでしばらくこれでがんばろうと思います。うまくいくとよいなあ。
Leslie2103mk2のプリ管かえました
同様に小型レスリースピーカー2103のプリ管12AU7も国産にかえてみました。
安心のヤフオクです。
今回は東芝でございます。初の東芝。やはり国産なのでまろやかでした。
もともと2103はパワフルで低音が強すぎるところもあったので、結果いい感じになったと思います。上から下までまろやかな音です。先日導入したハコとも相まってかなり幸せな響きかもです。
レスリー2103の下用にハコ作った
小型レスリー2103mk2は一人でも運べるのだけど、やはり大きい箱の鳴り方はしないわけです。
たまにステージの台の下が空洞のところだとこのスピーカーでもよい響きがするので、試しに下にハコを作ってみようとなりました。
これが
こんな筒状になって
こんな感じになります。
試作品なのですが、塗装も簡単にしてみました。材料の関係上、今回高さは45センチと低めです。
低音ハコの分だけ豊かになったかな。
足鍵盤の立ち上がりもちょっとHammondB3に近づけたような。
最も大きいハコでも試したくなりますね。
ちなみに密閉の箱が下について、下向きの音が全部そこにいくので、同じ高さのイスにおいたほうが広がりのある大きい音にはなります。ただ箱鳴りがあるこちらの方が、ぎゅっとした音になっています。変な帯域で音が膨らんだり、きこえなくなったりが起こりにくいかもですね。
レスリーらしく、下の方にスリット設けて少し音を逃がしたり、従来の開口部や、スピーカーの前にアクリルの板とか貼ってみた方が下とのバランスとれるかも。
この改造いろいろ楽しみが広がります。
低音がこれでよくなってくれたらツアーで2103しか持っていけない時でもよりよい音でできると思います。
レスリー2103mk2ドライバー交換
小型レスリースピーカーレスリー2103の音を何かの折につけてもう少しよくしようという計画です。
ビンテージレスリーのドライバ(高音用のスピーカーみたいなの)を好みのものに換えたときに余ったのがatlas PD5VH。これの大きさがちょうど2103に入りそうだったので試しにつけてみました。
もともとPDはビンテージレスリー用のリプレースとして評価が高いので、期待大です。ただもともとのドライバが12ΩにたいしてPDは16Ω。出力下がるのだろうか。
結果として、もともと音量も半分強で使ってたこともあるのか、音量はほぼ変わらず、むしろなぜか歪みのポイントは早まったような気がする。なぜだろう。
そして低音が増えた気もする。気のせいだろうか。
肝腎のドライバの音は圧倒的にPD5VHの方が好みだったので、とりあえずこのままで行こうと思います。
設計と違う抵抗なので気が引けるのですけど、まあよいとしましょう。